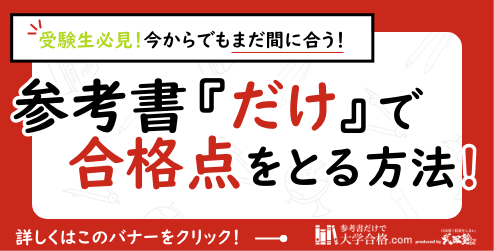ご無沙汰しております。上越校講師の町です。
新潟県といっても広いですし上越市といっても広いので地域により差はありますが、校舎がある上越市の旧市街地・高田では、今年の冬は割と雪が積もり、私も愛車が特に雪道に強い四輪駆動車であることを過信して車庫前の除雪を適当にしていたら、少し気温が上がって雪が緩んだ日に出かけようとして、車庫前で完全に身動きが取れなくなり日本自動車連盟(JAF)様のお世話になってしまいました。
そんな2月も終わり、3月も半ばを過ぎましたが、まだ寒い日が時々あります。
ですが、上越校は本当に熱い冬でした(詳しくは上越校の合格実績をご覧ください)
というわけで、受験生の皆様、大変お疲れ様でした!!!
残念ながら進路が決まらず1年延長で浪人される方もいらっしゃると思います。
武田塾では無料受験相談をやっています。
次の1年の学習計画の参考にしたいという軽い気持ちで相談に来ていただければと思います。
結局、志望校合格という目標達成の最終段階は自分で過去問を解けることであり、
できないことができるようになるには、段階を踏んでステップアップしていくしかないんです。
私たち講師はそのペースや習熟度を管理し、また、皆さんの志望校の過去問を分析してさらに必要となる能力を身につけるサポート・コーチング・正解を導くための解法を解説をしています。
※武田塾上越校では皆さんの志望校の過去問を難関国公私立大学の過去問まで各科目担当の講師が実際に解いて分析し、攻略法を指導しています。
(ここまでの話はタイトルとは関係ありませんからね!!)
他方、幸運にも無事に合格された皆様(失礼か!実力じゃい!)
中には、故郷を離れ、遠い知らない土地で春から一人暮らしを始める方もいらっしゃるかと思います。
あなたたちは18歳、人によってはまもなく19歳になる人もいます。
令和4年から施行された改正民法により、18歳以上が成人となりました。つまり18歳以上は大人として扱われます。
高校でも言われたかもしれませんね。
これが意味するところは、「あなたの意思表示は未成年者として保護されない」ということになります。ちょっと難しいですね。
日本という国は、行き過ぎた自由であるところの「新自由主義」である、というのはおいておいて、基本的に自由主義です。
自由というと大変聞こえがいいですが、自由な選択には責任が伴います。自由とは大変怖いものです。
今あなたは受験勉強から解放され、高校も卒業し、時間的には限りない自由を得ていますが、自由な時間に何をしたらいいのかわからないという声をよく聞きます。そんな「限りない自由」は、万人が享受できるものではないのです。
限りない自由というと、また「新自由主義」の5文字がチラつきますが、限りない自由を謳歌できるのはお金と時間がある人です。
ところが多くの場合、お金はあるけど時間がない、もしくは、時間はあるけどお金がない、のいずれかの状況にあるのが標準的な日本国民だと思います。
前者は、お金があるのでしばらく仕事を休めば一定期間は最大限の「限りある自由」を謳歌できるでしょうが、後者は、そうはいきません。
ならばお金を稼げばいいじゃないかという発想になりがちですが、お金を稼ぐことが目的になってしまった結果、いかにラクをしてお金を稼ぐかという発想になってしまったのではないでしょうか。
令和日本は社会機能のバランスが崩れつつあります、というかすでに崩れています。
第1次産業のなり手がいなくなれば私たちの食はどうなってしまうのか。第2次産業のなり手がいなくなれば私たちの家や服、車など、日々の生活を支える工業製品なくして高度に発展した社会を維持できるのでしょうか。
以前は第3次産業に働き手が偏っていると言われていましたが、小売業や飲食店の現場では特に地方部での人手不足が顕著です。時給が1300円の求人にさえ応募がないと聞きます。
このまま一億総ホワイトカラー、一億総YOUTUBERになったらどうなるか、考えたことはあるでしょうか。
社会を維持できなくなることはわかりますよね?
確かに、私たちの職業選択の自由は憲法22条1項によって保障されています。職業選択の自由は経済的自由であると同時に、個人の人格的価値と不可分でもあることから、この自由に対する制約は他の経済的自由に比べやや厳しめの違憲審査基準が用いられます。
国が社会の維持のために国民の職業選択を制限するようなことをすれば違憲訴訟に発展するでしょう。
ではどうすれば良いか。国が社会維持のために人手が必要な産業に対しお金を出し、高待遇の求人を可能にするしかないのです。
しかも1次産業は我々の生命に直接関わるものであるところ、その従事者は公務員と同等の身分保障があってしかるべきなのです。
ところで、「限りない自由を謳歌するお金持ち」を支えているのは、自由が制限された「お金持ちでない人たち」です。
竹中◯蔵さんでしたか、何年か前に「貧乏になる自由もある」などと宣っておりましたが、その日食べるモノも買えないくらい貧しい、いわゆる最低限度の生活を下回る暮らしを国が保護しない場合憲法25条違反になりうることは、高校生以上の方なら誰もが知っていることと思います。この方はご存知ないのか、そういう世界が嫌なのかもしれませんね。
限りない自由を指向すると、結局強いものが勝つという弱肉強食の世界が出来上がるのです。さきの竹中○蔵さんのように、現に世界は弱肉強食で回っていますが、国民の間で勝ち組と負け組を作ることは、国・国民を分断し、結果として国力が低下することになります。これは国のGDP(4位)と一人当たりGDP(39位)が乖離している日本においては非常にわかりやすく実感できるかもしれません。
(ちなみに、GDP1位のアメリカの1人あたりGDPは6位、3位のドイツでも1人あたりGDPは17位です。なおGDP2位の中国は1人あたりGDPが73位)
みんながある程度幸せであればいいじゃないかという、高度成長期の「一億総中流」という思想は、いわば社会主義的に聞こえがちですが、自由というのは本来「ある程度の規制の上に成り立つ」ものであるというのは日本国憲法12条・13条・22条などにみられる「公共の福祉」という文言にも表れています。
自由が限りないのであるとすれば、新興宗教の信者によるテロも憲法20条の信教の自由で保障されることになります。
ですが、30年前のオウム真理教によるサリン事件では実行者と首謀者らが処罰されましたし、団体の解散命令も出されましたが合憲とされました。これは、信教の自由への制約ではあるけれども「公共の福祉」に照らした判断だからです。憲法に違反するか否かというのは、制約される人権の重要性によって判断基準が変わってきます。
これを違憲審査基準と呼ぶことは、政治経済などでも学びましたよね?
この点、19条の「思想良心の自由」は「侵してはならない」と規定され、これは内心においては絶対的に保障されると解釈されます。制限的な自由の例外です。ただし、あくまで内心においてなので、それが外部的な行為としてなされた場合には制限される余地があります。
なお、財産権を定める29条も1項で「これを侵してはならない」と規定するところ、これは現に有する財産を保障すること、及び私有財産を制度として保障することを意味します。この私有財産の核心は、通説的には生産手段の私有をいうと解されていますが、国家権力などによって生産手段が奪われることはないというのは、憲法を改正しない限り社会主義体制には移行しないということです。従って、29条1項は個人が現に有する財産を不当に権力に奪われることはないということが規定されているにすぎず、正当な形で収受する場合は「財産権を奪う」ことにならないと解されます。
自由というのは本来「ある程度の規制の上に成り立つ」と述べましたが、かつては規制により守られてきた産業というのがありました。主にインフラです。
代表的な日本国有鉄道は1987年に分割民営化されJRとなりましたが、大都市圏を持たないいわゆる三島会社(JR北海道、四国、九州)の経営が不安定になるのは、モータリゼーションの発展に鑑みれば目に見えていたはずです。
現代では、あろうことか水道が民営化される事例もありますが、私たちの生命の源でもある水道が民営化されると、儲かっていないから古い水道管を交換しないという理屈がまかり通ってしまいます。民間事業者は利益を追求することが目的なのですから、当然ですよね。
何でもかんでも自由を尊重すると、結局は力関係の強い者の自由が優先されてしまうのです。
水道事業者はいわば市民の命を握っています。民間の水道事業者が利益を追求する自由と、市民が健康に害のない綺麗で美味しい水を得る自由とが衝突した場合、自由に制限がなければ、両者の自由は水道事業者に有利に傾くことは理解できますよね?
他方、水道事業者を市という公が担っていれば、市場原理に左右されないので、必要な箇所に予算をつけて我々の税金で運営することができます。
地方公共団体は、国と違い通貨発行権がないので、限られた予算の中でやりくりをするしかありません。
そうだとすれば、観光で人を呼ぶ、ということと、道路やガス水道管、LED化した防犯灯の交換費用など電気設備、といった安全なインフラの維持管理、どちらが優先されるべきなんでしょうかね。今年は我が上越市、市長選挙があります。
そこで本題です(強引)
実は大人に認められている自由が未成年者に対しては制限されていることが少なくありません。
これは未成年者の知慮浅薄、すなわちしっかりとした考えと自己責任のもとに行動することがまだできないとされていることから、さまざまな法的保護がなされています。なお成人であっても、正常な判断ができないと判断された者は段階に応じて行為の自由が制限され、法的に保護されています(成年被後見人、被補佐人、被補助人)。
まず、未成年者が法律行為(例えばさまざまな契約など)をするには法定代理人(例えば親)の同意を得なければなりません(民法5条1項本文)。ただし、単に権利を得(例えばパソコンを譲り受ける)、義務を免れる法律行為はこの限りでない(民法5条1項但書き)。
例えば、16歳の高校生が親の同意を得ずにバイクを買ったとしましょう。この場合、売り手は通常、買い手であるその高校生に親の同意書をもらってくるように請求します。目的を定めて処分を許した財産(おつかいのお金のこと)はその目的の範囲内でしか処分を許されていません(5条3項前段)が、目的を定めないで処分を許した財産(お小遣いのこと)を処分するときは未成年者が自由に処分することができる(5条3項後段)ので、バイクの代金全額が貯金したお小遣いでの支払いであればその高校生はバイクを買うことができます。もっとも、基本的にバイクという高額商品である性質上、お店は親の同意書を求めるでしょう。これは後で揉めることを防ぐためです。
他方、大人であっても取消権が認められる場合があります。典型的なものが詐欺です。
この点、単に騙されたことをもって詐欺というのが日常的な使われ方ですが、正確には騙されたことによって財産的な損害が発生していなければ詐欺とは言えません。
興味深いのが詐欺は民法にも刑法にも規定があることです。
刑法上の詐欺罪は刑法246条に規定されていますが、これは詐欺を働いたものに刑罰を与えるための要件であり、詐欺による意思表示の効力を取り消して、騙し取られたものを返してもらうというのは民事上の手続きになります。
民法上の詐欺は民法96条に規定されていますが、96条は詐欺以外に強迫というのも並列に規定しています(なお、民法上は強迫と表記されますが、刑法上は脅迫と表記されます。めんどくさいですね)。民法上の表記と刑法上の表記が微妙に違うのは、それぞれの法律の役割が違うからと思われます。民法は私人と私人の争いを解決するための法律であり、刑法は何をどのようにすれば犯罪に当たり、犯罪を犯した者がどのような処罰を受けうるかを国民に提示するものです。刑法が脅迫とするのは単に強く迫るでは足らず、脅すくらいの迫り方であることが犯罪に値するという価値判断の表れなのでしょう。
民法96条に戻ります。
まだ少し法律論の話をしますが、法学部でなくても、あらゆる学部に進学される皆さんはちょっと覚えておくといいかもしれません。民法は私たちの日常生活の行為に関わりますし、経営や商学部に進学する人は商法的な講義もあると思いますが、商法は民法の特別法という位置付けなので、民法的な考え方を持つことは大切です。
民法96条1項は「詐欺または強迫による意思表示は取り消すことができる」と規定しています。
ところが、2項では「相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合・・・相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる」と規定しています。「強迫」は対象外です。
これは、AとBとの間において、例えばAの意思表示がCの「Bと○○したら毎月1万円分のペイ○イポイントが付与される」という詐欺によって、Bとの間で意思表示がなされた場合、AがCの詐欺によってBに意思表示をしたということをBが知っているか知ることができた場合のみ、Aはその意思表示を取り消すことができるというものです。かなり限定的な場面ですよね。例えばBとCが裏でグルになってAを騙しにかかった場合です。この場合、何も知らずにAの意思表示に応じた場合に比べ、Bを保護する必要性が相対的に下がりますよね?
また、3項では「・・・詐欺による意思表示の取消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない」と規定されています。なんだか読み飛ばしてしまいそうですが、ここでも「強迫」の文字がしれっと消えているのです。
この「善意」とは法律用語で「知らない」という意味、「第三者に対抗できない」とは、「あなたの権利は第三者の権利より弱いです」という意味だと思っておいてください。AがBの詐欺によって騙し取られたものをAが取り返そうとしても、その騙し取られたものがBから過失なく事情を知らないCに転売されていた場合にはAは詐欺取消しによってはもう取り戻すことができないということです。
Cさんは事情を知らないので「善意」であり、過失もありません。「第三者」にも定義があるのですが、これはまあいいでしょう(一応念のために書いておくと、「当事者もしくはその包括承継人以外の者であって、詐欺による意思表示の後、新たな独立の法律上の利害関係を有するに至った者」となります)。例えばAがBから「あなたの土地はこれから価値が下がる。今のうちに処分して財産を守った方がいい」と持ちかけられ、Bにその土地を売ったとします。ところが実際は付近に地下鉄の延伸と新駅設置計画があって土地の価格が爆上がりすることが確実だったとしましょう。Aは土地を取り戻したい。そこで96条1項により、詐欺による意思表示を取り消すことができます。ところがこの意思表示の前にBが第三者Cに土地を転売していたとしましょう。このCが「第三者」にあたります。また、Cはこの土地がBがAから騙し取った土地であることは知りませんので「善意」であり過失もありません。Bに詐欺をかまされたAを保護するか、Bから転売されたCを保護するか、という場面で、Cを保護するというのが96条3項の効果です。
他方で、強迫というのは、意思を抑圧されている状態です。
「おい!この土地建物を売却しろ!」というものです。
この場合、強迫された者に落ち度はないですよね?純粋な被害者と言えます。
一方で、詐欺をかまされた被害者は自分も金儲けができるという利得感情があったといえるため、保護の必要性が弱くなると解されています。どっちも同じくらい保護すればいいじゃん、という優しい方もいるかもしれませんが、同じ条項の中であえて差別化したのは、「騙される奴が悪い」という価値判断の表れと言えると思われます。
ちなみにタイトルは騙す奴も悪いとなってるけど
この元ネタは「詐欺は騙す方が悪いんやない、騙される方が悪いんや」であるところ、コンプライアンスに配慮してマイルドにしてみました。
元ネタは私が愛してやまない不朽の金融Vシネマ「難波金融伝 ミナミの帝王」で竹内力さん演じる萬田銀次郎のセリフです。
全60作品ある中で、この詐欺についてのセリフは複数の作品に出てきます。
この作品は法的知識が数多く出てくるため、作品の制作にあたり法律監修というポストがあります。その法律監修を担当していたのが山之内幸夫さんという、当時、とある大きな反社会勢力(俗にいうヤ○ザ)の顧問弁護士をやっておられた方です。
その方の社会に対する啓発だと私は思っています。
騙されるというのは隙があるからです。だからあなたの隙は善意無過失の第三者との関係で保護されないのです。
ところが、未成年を理由とする取消しには、第三者保護規定がありません。
例えば、中学生が親からもらった高価なカメラをお金欲しさに現金化しようと、近所のカメラ好きのおじさんに売ったとしましょう。そしてそのおじさんが甥っ子に譲ったとします。この場合、中学生が「やっぱ取り消すわ」と意思表示をすれば、元の持ち主が中学生であることをこの甥っ子が知らなかったとしても、当該善意無過失の第三者たる甥っ子は保護されず、元々の権利者である中学生の所有権が保護されることになります。ここが、未成年者が成人よりも保護されていることの表れなのです。
春から故郷の実家を出て一人暮らしを始めると、寂しさで心に隙ができます。変な勧誘に遭わないように気をつけましょう。
怪しいビジネスのセミナー、悩み相談や自己啓発と見せかけた新興宗教の勧誘であることもあります。
あっち系のサイトを閲覧していると急に画面に「あなたの端末はウィルスに感染しました」などと表示され、手順に従ってウィルスを除去しましょう、ただし除去費用が10万かかりますというものもあります。人の不安につけ込みやがって・・・本当に地獄に落ちろと思います(なんかあったんか?)
一人暮らしを始めると、全てが自由です。少しバイトで稼げたからといってつい使い過ぎてしまう。すると、金欠に陥ります。
財布や口座にできた隙を埋め合わせるため、怪しいバイトに手を染めてしまう。それが詐欺をする側に加担していることもありますし、詐欺をされる側になっていることもあります。
人は、おいしい話なんて、他人に話したりしません。
すなわち他人から持ちかけられたおいしい話には必ず裏があるということを忘れないでください。
本当においしい話もあるかもしれませんが、おそらく地球外生命体を見つけるより困難だと思います。
そしておいしい話というのはそれを見つけた最初期の人間たちに恩恵があるだけで、後追いで乗っかる人たちが手にする利益などほとんどありません(むしろ損失が甚大であることが多い)。
お金を稼ぐというのは大人になったら嫌でもやらなければいけません。生きていけないのですから。
他方で、学生の間にしかできない経験があります。それはインターンとかそういう社会に出るための準備といった類のものではなく、万物と向き合うことを許された時間の中で、心に従った自由な選択が、その後の人生における非金銭的な意味での豊かさをもたらすという意味での経験です。
○○がしたい!と思ったら、まず、実現するための可能性を洗い出してみましょう。
人生は行動力と決断力です。