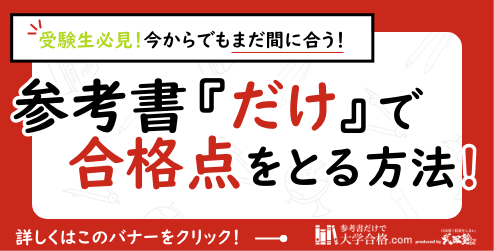受験生の皆さんなら、今までテストや模試で一度は「悪問」に出会ったことがあるのではないでしょうか。
テスト中に悪問が登場すると焦ってしまい、あまり良い点が取れなかったという方もいらっしゃるかと思います。
そこで今回は、「悪問」の定義や受験本番で悪問が出題されてしまった時の対策方法などをご紹介したいと思います。
万が一悪問に出くわしてしまった時のためにも、しっかりと対策を立てていきましょう。
悪問とは?悪問の定義や事例を解説!

「この問題は悪問だ」など生徒さん同士で言い合ったり塾の講師やネットの情報で見聞きすることも多いため、「悪問」という言葉を知っている人は少なくないと思います。
しかし、そもそも悪問とはどんな問題を指すのでしょうか?
この項目では、悪問とはどんな問題なのかを解説し、悪問と一緒にされやすい「難問」「奇問」の定義やその違いを紹介していきます。
「悪問」とは?
悪問とは、簡単に言うと「一般的に解けない問題」のことを言います。
明らかに適切な難易度を逸脱していたり、解答のための材料が不足しているような問題が悪問に該当します。
そもそも問題自体が間違っていて絶対に解くことが出来なかったり問題文の文章がわかりにくく複数の答えが存在してしまうような問題も悪問として扱われます。
非常にマニアックな知識を問われるような問題も悪問と呼ばれることがありますが、こちらは「奇問」とも呼ばれています。
「難問」「奇問」とは?
「悪問」と似た言葉として「難問」「奇問」がありますが、これらの言葉の意味の違いを解説するためにここでは「難問」「奇問」についての定義を紹介します。
まず「難問」とは、純粋に難易度が高い問題のことを言います。
解ける・解けないにかかわらず、難しい問題であれば「難問」と呼ぶようです。
「奇問」とは、普通では出題されないようなマニアックな知識や解き方をする問題のことを指します。
「難問」「奇問」「悪問」の違いは?
「悪問」は「難問」や「奇問」よりも”理不尽に難易度が高い”や”問題自体に不備がある”というようなニュアンスを含んで使われます。
例えば、難しいけれど一応解けるなら「難問」となりますが、その試験で問われるべきレベルからかけ離れておりほとんどの人が解けないなら「悪問」と言えます。
それ以外にも、難しいかどうかや知識のマニアックさに関わらず問題文の説明不足や不備がある場合にも悪問として扱われることが多いです。
「難問」「奇問」は問題の難易度で判断することが多いですが、「悪問」はそれに加えて問題そのものの不備などでも判断されるのが主な違いと言えるでしょう。
悪問が出題されたらどうする?解く必要はあるの?

模試や受験本番で悪問に出会ったら、どのように対応したらよいでしょうか?
「これは解けないんじゃ?」と思うような問題が出題されてしまうと、パニックになってしまって闇雲に試験の時間を使ってしまうかもしれません。
もし受験本番にそのような事態に陥ったら、点数に大きく影響してしまいます。
ここでは悪問に遭遇したときに解くべきか解くべきではないかを解説するので、これから受験本番を迎える受験生の皆さんはぜひ覚えておいてください。
悪問=捨て問。解く必要は全く無い!
結論から言ってしまえば、悪問を解く必要は全くありません。
そもそも悪問は問題文に不備がある、理不尽に難易度が高い問題のことなので、自分だけでなく周りの受験生も解けない人が多いはずです。
大多数の人が解けないであろう問題に貴重な試験の時間を割くよりも、確実に解ける問題でこつこつと点数を稼ぐ方がいいでしょう。
そのため、悪問が出てきたら迷わず”捨て問”として割り切って、他の問題を解くのに集中することをおすすめします。
悪問の見分け方やその対策は?
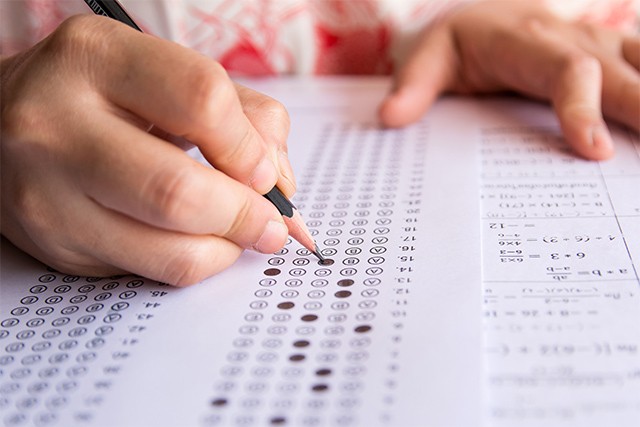
悪問が出てきたら捨て問として無視することが最善の対応ですが、そのためには今解こうとしている問題が悪問かどうかを見分けられないといけません。
悪問であるという判断をすぐに出来ないとそれだけで時間を取られてしまうため、悪問をすぐに見分けられるようにしましょう。
この項目では、悪問を見分けられるようになる方法や悪問を見分けるようになるためのコツと対策方法を3つご紹介したいと思います。
模試で悪問に出会って不安になっている方や受験本番を迎えようとしている方は参考にしてみてください。
悪問の見分け方・対策方法①問題集・過去問を一通り解いておく
先ほどの項目でご紹介したように、悪問とはその大学のレベルより逸脱して難しかったり内容に不備が合ったりする問題です。
これを見分けるためには、受験の事前準備として受験する大学の過去問や同じレベルの問題集を一通り解いておく必要があります。
問題のパターンを把握しておくことで、悪問が出た時に瞬時に判断できるようになれるでしょう。
その大学に十分合格できるレベルの学力に達していれば、そのレベルから逸脱している問題をすぐに悪問だと判断して捨てることができるでしょう。
悪問の見分け方・対策方法②問題文の不備を感じたら悪問の可能性アリ
悪問のパターンとして”問題文の不備”というものもあります。
難易度や出題形式以前に、そもそも問題が何を言いたいのかわからない時は悪問かもしれません。
ごく稀にですが、正解が複数あったり、逆に適切な正解が無かったりなど問題自体に不備があり、大学側が謝罪するというケースもあります。
このような場合にはその問題は全員正解扱いになることがほとんどなので、必要な要素が足りなくて解けないな、文章が変だなと感じたらすぐにその問題からは離れましょう。
悪問の見分け方・対策方法③解ける問題から解くという習慣をつける
受験のテクニックとして、「解ける問題から解く」という習慣をつけることはとても大切です。
受験は必ずしも100点を取る必要はなく合格点に到達していればよいので、自分が解ける問題から解いていって確実に点数を稼いでいく必要があります。
難問・奇問・悪問と呼ばれるものは確実に解ける問題を解いて余った時間で取り組むのがおすすめです。
この判断を受験本番で急にするのはなかなか難しいので、模試の段階で「解ける問題から解く」という意識で試験に取り組みましょう。
早慶など難関大学は悪問が多いかも?

早慶を中心とした難関大学の試験では、教科書にも載っていないような非常にマニアックな問題が頻繁に出題されます。
これらの問題は一般的な対策では解けないため、奇問や、時には悪問として扱われることもしばしばあります。
悪問・奇問と呼ばれるような問題が出題されやすい大学は存在するので、そういった大学を志望している方は特に悪問・奇問に対しての対策方法を考える必要があるでしょう。
難関大学が非常に難しい問題を出題するのは当然のことですが、その中でも自分の得点源を確保しつつ悪問かどうか判断できるよう過去問などの事前準備をしっかりするようにしてください。
受験本番で「悪問」はつきもの?悪問の定義と対策方法を解説!|まとめ
悪問とはそもそも解くことができないような問題で、
・適切な難易度を超えた理不尽な問題
・問うべきではないマニアックな知識が必要な問題
・問題自体に不備があり解答不能な問題
などの問題のことを言います。
悪問は時間をかけるだけ無駄になってしまうため、見かけたら諦めて他の問題に時間を使うことが何よりも大切です。
ぜひ今回ご紹介した悪問への対策方法を参考に、受験の準備を進めていってください。