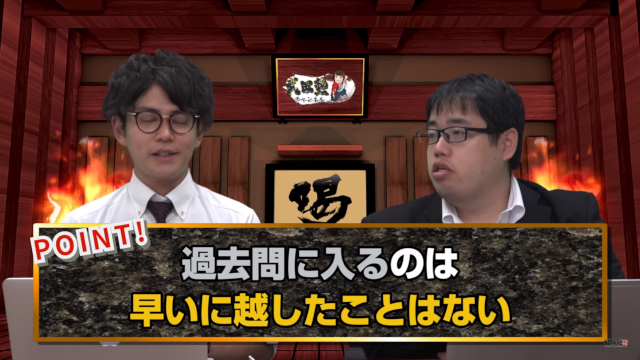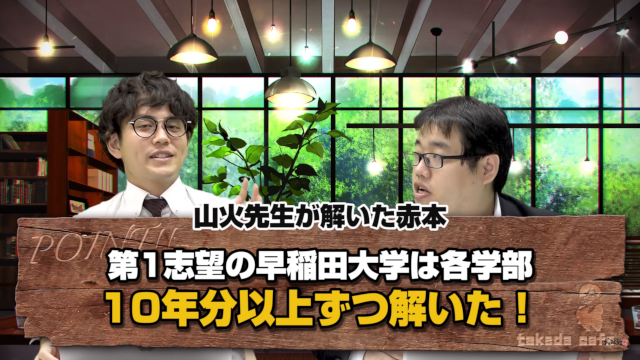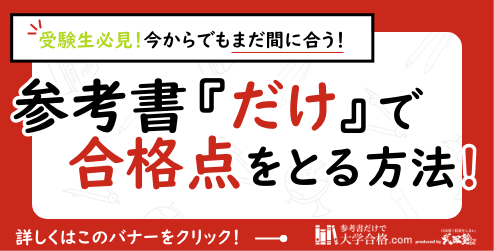受験勉強で使う過去問集と言ったら「赤本」が有名ですが、いったい赤本はいつから手を付けるべきなのでしょうか。
今回は赤本をいつから始めるべきか、何年分やるべきかなど赤本の解き方について詳しく解説していこうと思います。
過去問は志望校の傾向を掴み、合格できる可能性を知るための大切な材料です。赤本の解き方を知り、上手く活用できるようにしていきましょう。
赤本(過去問)はいつから始めるべき?
赤本(過去問)の勉強は、いったいいつから始めれば良いのでしょうか?
ズバリ、過去問を解きはじめるのは早ければ早いほど良いです。
志望校や勉強の進度は人によって違いますが、9月には一度過去問に入っておきましょう。
目安としては、まずは週に1年分のペースから始めるのがおすすめです。
第一志望の過去問にチャレンジすべき理由
「いきなり過去問を解きはじめても、解ける自信がない…」という人もいるかもしれません。
しかし、解ける解けないに関係なく、志望校の過去問に触れておくことがポイントです。
たとえば「最終的には早慶を目指しているけど、まずはMARCHルートからやっている」という人でも、早慶の過去問は早い内から解き始めておきましょう。
「MARCHレベルの実力確認のためにMARCHの過去問を解く」というのも勿論必要ですが、第一志望の過去問はそれとは別で考えなければなりません。
というのも、第一志望の過去問に触れることで、「今の自分には何が足りないのか」「何を勉強すれば解けるようになるのか」ということが浮かび上がってくるからです。
自分の課題を明確にし、モチベーションを上げるためにも、勉強の進度に関係なくあくまで第一志望の過去問にチャレンジするのが重要です。
赤本は何年分やるべき?
では、赤本は何年分くらい解けば良いのでしょうか。
時間の許す限りたくさん解きたいところではありますが、併願校の分まで対策することを考えるとそれぞれの大学にかける時間配分が大切になります。
また、たくさん解きたいけれどそもそも過去問の数が少ないという場合もあるので、そのようなときにどう対策するのかがポイントです。
第一志望は10年分、それ以外は5年分を目安に
基本的には第一志望にたくさんの時間を割きたいので、10年分を目安に過去問があるだけ解き進めましょう。
ただし問題が古すぎると傾向もかなり変わってきます。10年違うと傾向もほぼ別物と考えて良いので、その点は注意してください。
第二、第三志望は5年分が目安です。
第一志望の赤本も解いて、足りない部分の復習をすることも考えるとかなりの量になりますので、計画的に進めていきましょう。
一度にやる量は2年間分を目安に!
また、一度に解く量は2年間分を目安にするのが解き方のポイントです。
過去問は問題やその年の傾向、自分の得意不得意によって取れる点数がかなり上下してしまうことがあります。
たまたま得意な問題や不得意な問題が出てしまうと、現在の自分の正しい実力がわかりません。
また、「その年だけ易化した、難化した」というケースもあります。
志望校ごとの完成度をしっかりと把握するためにも、一度に2年間分ほど解いて平均的な点数を参考にするという解き方をすると良いでしょう。
「この大学のこの学部なら、〇〇〇点くらいとれそうだな」という大体の目安を把握しておくのがポイントです。
過去問が手に入らない時は?
第一志望は過去問を10年分解くべきとは言え、どうしても10年分も手に入らないこともあるかと思います。
赤本は直近数年間分しか収録されていないので古本を手に入れてくるのが理想的ですが、手に入らなかった場合の対策法をご紹介します。
傾向に似ている大学・学部の過去問を代用しよう!
もし過去問が十分に手に入らなかった時は、傾向の似ている大学や学部の過去問を代用することをおすすめします。
私立大学、特に関関同立やGMARCHなどの大学は同じ大学の学部間で問題傾向が似ていることが多々あります。
新設したての学部などでは過去問が少ないので、同じ大学で分野の近い学部の過去問はかなり参考になります。
国公立の場合では理系・文系で過去問がそれぞれ1パターンずつしかないので、傾向が似ている他大学を探し出してそこの過去問を参考にすると良いでしょう。
赤本は解いて終わりにしない
上述の通り、過去問はたくさん解いておいた方が有利ですが、かといって数をこなすだけになってしまってはあまり意味がありません。
赤本を解き終わった後は、必ず復習や分野別の対策をしましょう。
大切なのは、赤本を丸暗記することではなく、各大学の問題の傾向や、今の自分に足りないものを認識することです。
赤本を1冊解けば、問題の傾向や出題パターンを大体掴むことができるので、それを普段の自習に活かすことが、最も重要です。
「赤本を解く→復習・分野別対策」を繰り返すことで、合格点がとれるところまで自分のレベルを押し上げていきましょう。
赤本の解き方まとめ
赤本に入るのは、早ければ早いに越したことはありません。
解ける解けないに関わらず、「志望校の過去問に触れておく」ということが大切なので、遅くとも9月までには一度、第一志望の過去問に入っておきましょう。
過去問を解く量の目安は、第一志望で10年分、第二第三志望で5年分とかなりの量ですが、たくさん解いておいた方が有利であることは確かです。
ただし、勿論数をこなせば良いというわけではありません。
赤本を解いて終わりにするのではなく、復習や苦手分野の対策にどう活かすかが、志望校合格の鍵となります。
いかがでしたでしょうか。ぜひ今回ご紹介した赤本の解き方を活用して志望校の傾向を掴み、合格に一歩でも近づけるように頑張ってください。